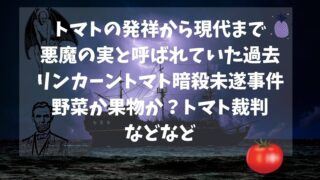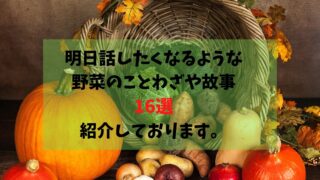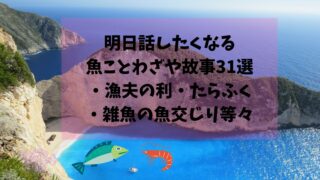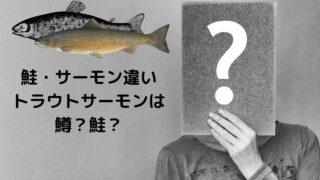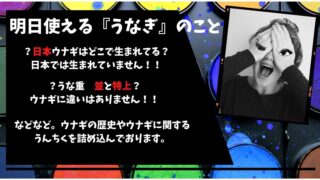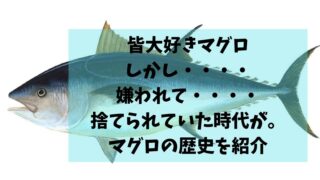カレーやポテトサラダ等の材料として用いられ、日本人にはなじみの深いじゃがいも、そんなじゃがいもですが多種多様な種類がありそれぞれに特徴があるのです。現在作られていないものなど含めるとその品種は日本だけで200品種を超えます。よりよい品種が出ては新しい品種が栽培されています。
今回はそんなじゃがいもの選びからを、料理から選ぶ方法と新鮮なじゃがいもを見極める方法を紹介いたします。
料理から見るじゃがいもの選び方
じゃがいもは様々な料理に仕える万能野菜ですがその用途は広く、肉じゃが、カレー、シチュー、おでん、味噌汁などの具、ポテトサラダ、グラタン、フライドポテト、マッシュポテト、ヴィシソワーズ、コロッケ、トルティージャ、パスタ(ニョッキ)など幅広い料理に利用されているじゃがいもですがその品種によって食感や味などが異なるため、料理によって芋の選び方が変わってきます。
じゃがいもの種類は大まかに3つに分けられる。
じゃがいもは食感が粉質、粘質、中間と大まかに分けられます。それぞれに特徴があるため料理にあったじゃがいもの選び方を考えるといいでしょう。この3つの他加工用に栽培されているじゃがいももあります。
粉質のじゃがいもとは?
でんぷん質が多く食味が粉っぽくゆでたり揚げたりするとほくほくした食感が得られるのが主な粉質系のじゃがいもの特徴です。
主な品種として男爵いもやキタアカリなどが挙げられます。基本的に煮崩れしやすい品種が多くあまり煮込み料理などには向いていないといえます。逆にこふき芋やコロッケなどあえて潰して調理するものに向いているものが多いです。ただ中にはホッカイコガネのように粉質であるにも関わらず煮崩れしにくい品種もあります。
粘質のじゃがいもとは?
粘質のじゃがいもは粉質とは逆にしっとりとした舌触りが特徴です。茹でたものを練ったりするとくっつくような感じになるタイプの種です。
主な品種としてメークインなどがあります。煮崩れしにくいので煮物やカレーなど煮込む料理に向いている品種が多いです。

中間質のじゃがいもとは?
中間質のじゃがいもは粉質と粘質の中間を指し、強いほくほく感などはなく、かといってねっとりとして食感も強く感じないです。こうしたタイプの種は煮物などにもあい、つぶして使ってもそれなりに美味しくいただける場合が多いです。ある意味使い勝手のいい品種と言えるでしょう。
主な品種としてグランドペチカやノーザンルビーなどが当てはまります。
じゃがいもの選び方

食品にはおいしく食べれる時期や、状態があります。
それはじゃがいもも然り、そこで今回はじゃがいもを安心して食べれるようにじゃがいもの選び方をお伝えしたいと思います。
新鮮なものを選ぶ
じゃがいもに限らず野菜は新鮮なものがいいです。特にじゃがいもには新鮮でないとよくないデメリットがあるので注意が必要です。
芽が出ているものは注意が必要
じゃがいもの芽にはソラニンという毒素があり食べてしまうと吐き気や腹痛、頭痛などの症状が出るだけでなく最悪死に至るケースもあるので注意が必要です。また芽が出ているものは芽に栄養分が取られているため食味が落ちます。逆に芽が出る直前のものはデンプンの糖化作用が進んでいる状態で甘みが増します。
皮はしわがない物を選ぶ
皮にしわがあるということは、古くなっている、または適切に保存されていなかったなどが挙げられるため皮がなめらかなものを選ぶとよいです。
皮が緑化していないか確認
皮が緑色に変色しているものが時々スーパーなどにも売っていますが、皮が緑色になるということは、太陽や蛍光灯などの光を多く浴びていることが原因で、緑化した部分にもソラニンの含有量が多くなっています。買ったじゃがいもが緑色に変色してしまった、または皮が緑色になったじゃがいもを買ってしまった場合は変色した部分を気持ち多めに剥いて使うようにしましょう。間違っても皮ごと使う料理には使用しないことです。
皮は薄さを感じるものを選ぶ
種類により皮の厚さは違いますが、なるべく皮が薄いと感じるものを選びましょう。これは生育しすぎていると皮が厚くなるためです。
皮がもともと薄い新じゃがの見極め方
もともと皮が薄く、皮ごと調理して食べれる新じゃがの基準は皮が指ではがれそうなくらいのものが良いです。古くなるにつれて皮が厚くなりはがれにくくなります。
良品を見極める
野菜などは作る際の環境や天候などに大きく作用されるため、どうしても品質に差が出てしまいます。そこでどういったものが良質なじゃがいもなのかを知ることで安心でおいしいものを手にすることができます。
重くて重量感のあるものを選ぶ
じゃがいもはさわって硬さがあり重量感のあるものが良品です。軽くなっているものは水分が抜けていたりするため軽くなり、皮にしわが寄っていたり柔らかくなっている場合などもあります。
でこぼこしているのはダメ
男爵芋のようにもともとでこぼこした品種はわかりづらいですが、例えばメークインなどなめらかな形の芋がでこぼこしていたり、形が不規則におかしいものは生育不良のため、購入する際はなるべく避けるようにしましょう。
大きいからいいとは一概に言えない
一個単位で販売されていて同じ値段のじゃがいもならば思わず大きいものをとってしまいがちですがこれも一概にいいとは言えません。
品種により差はありますが大きくなりすぎた芋は中が空洞になっていて黒くくすんでいたりする場合があります。
メークインなどの形が扁球なじゃがいもにはあまり見られませんが、男爵芋など球形でわりとごつごつしたタイプの芋の場合それが時折見られます。
また品種によっては大きくなると中心空洞が多くなる品種もあるので一概に大きいものがいいとは言えません。大きいものを選ぶ際は、手に取ってみて重さを比べるなどしたほうがいいでしょう。サイズとしては男爵芋の大サイズでも8cmくらいまでがちょうどいいサイズと言えるでしょう。
じゃがいもの適正に合わせて購入する
料理には季節ごとに旬や料理にあった食材などによりおいしくいただける状態があります。ですからその時々によってどのじゃがいもを選ぶかというのもポイントになってきます。
旬に合わせて購入する
じゃがいもは貯蔵がきくためいつでも購入できる野菜の一つではありますが、他の野菜同様に旬がある野菜です。
一般的にじゃがいもの旬とされる季節は10月~12月とされています。また冬に植えられて春先から初夏にかけて収穫される新じゃがと呼ばれるものは収穫時期が旬の為スーパーなどで、春先から初夏に新じゃがとして販売されているものがまさに旬なのです。
適正値段(スーパーなどで購入する場合)で選ぶ
品種などによって値段や大きさの差異はあるものの一般的なじゃがいもは4~5個入って200円~250円程度が一般的といえます。1個で50円前後、1kgだと400円前後くらいです。
これを大きく上回るようならそれは高級なじゃがいもなのかもしれません。高いじゃがいもにはそれなりに理由がありますが、合わない料理に使用しても宝の持ち腐れになってしまいますので高いものを購入するときは一度そのじゃがいもの事を調べてみるといいでしょう。
ちなみに世界一高いじゃがいもはフランスのラ・ボノットという品種で1kg約4万5千円です。これはA5ランクの松坂牛よりも部位に(ロースやヒレは高い)よっては高いお値段です。
保存食としてのじゃがいも
じゃがいもは凍結乾燥方が用いられてきた。先コロンブス時代、中央アンデス地域において、冷凍したじゃがいもを踏みつけることを繰り返すことで毒を抜く方法が発明され、長期にわたる保存、備蓄が可能になった。この凍結乾燥したじゃがいものことを「チューニョ」と呼ぶ。現在でもボリビアやペルーの高地では利用されている。また若干作り方が異なるものに「トゥンタ」と呼ばれるものがある、これもペルー南部やボリビアなどで広く食べられている。
日本の山梨県の鳴沢村や長野県の一部地域では同じように作られる「しみいも」、「ちぢみいも」があります。
じゃがいもはお酒にも利用されています。
じゃがいもが原料となるお酒はウォッカ、ジン、焼酎、ソジュなどで主に蒸留酒の原料に用いらています。この他じゃがいもを主原料としたじゃがいも焼酎やアクアビットと呼ばれる蒸留酒もあります。
じゃがいもの食べ方の注意点
じゃがいもの芽には毒素もありますので食べ方の注意点も記載しておきます。
じゃがいもは水に漬けすぎないこと
じゃがいもは、30分以上水に濡らすと、ペクチンと水に含まれる無機質が反応し細胞膜が強くなり火が通りにくくなりるので洗う際など水に漬けすぎないように注意しましょう。
じゃがいもは毒性がある部分が多数ある。
じゃがいもの毒性として、芽や皮にはポテトグリコアルカロイドと総称されるソラニン等の有毒なアルカロイド配糖体があり、緑色に変色した皮や芽は取り除く必要があります。その他食用にはなりませんが花などにも毒があります。
又、長期保存された芋では皮を熱く剥いて調理したほうがよいです。じゃがいもの毒性は強くないものの大量に食べて亡くなったケースもある為注意が必要であります。
じゃがいもは焦がしてはダメ
ポテトチップスなどに加工する際に焦がした時、中には発がん性物質の化合物になるニトロソアミンに変化することがあるので注意が必要です。このため焦げにくいポテトチップス用品種も存在しています。
薬用としてのじゃがいも
民間療法では湿疹ややけどなどの外傷にすったじゃがいもに小麦粉と酢を混ぜて患部に冷湿布します。また通風では食すとともに同じように患部にはることで軽減効果があるといわれています。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍ではすったじゃがいもの水分を飛ばして黒くなったものを1日1回2グラムほど服用するといいとされます。
じゃがいもの栽培について
じゃがいもは誰でも比較的育てやすい野菜で、春に種芋を植え付けて夏に収穫する春作と、夏に植え付けて秋に収穫する秋作があり、3月から7月までの春作の方が栽培しやすいです。栽培摘採温度は15~22度。植え付けを行う種芋は専用に育成されたものが使われる。種芋の数を意図的に増やすために、一般的には種芋は、芋に適度な温度と光を当てて発芽させ、目を中心にして適度な大きさに切り分けます。芋の腐敗を防ぐために切断面に灰などを塗布し、切断面を下にして置き、土をかぶせます。植え付け後、一つの種芋から多くの芽が出るため、生長の勢いがある太い芽を2本ほど残して抜き取る(芽かき)というのが一般的です。
地下茎は種芋より上に出来るためジャガイモを収穫するにはこの肥大する地下茎が日光に晒させないように株本の土を盛り上げる土寄せが行われます。花が咲き始めるころから肥料の吸収が盛んになり、追肥が行われる。新しい芋が大きくなったら収穫期で、株ごと引き抜きます。
大面積の耕作地ではハーベスターと呼ばれる収穫機械が使われ、上部の選別台で大きさごとに選別される。収穫語は、芋の水分蒸発防止や病原菌侵入防止のための表面処理が行われた後、低温貯蔵庫で一時保管してから出荷されるという流れになっています。
葉が緑の内に収穫した芋は長期保存が利かないため早めに食べる必要がありますが、地上部の茎葉が黄色く涸れるまで土中に置いた芋は、長期保存が可能な芋になります。
栽培にはpH6前後の酸性の土地が適しています。冷涼な気候や硬くやせた土地にも強い反面連作障害が発生しやすいの作物なのです。また、じゃがいもは病原菌が繁殖しやすく、保存状態の悪い種芋や収穫から漏れて地中に残された芋は病害の原因になる為、日本では植物防疫法の指定種苗となっているのです。
じゃがいもは連作に向いていない。
連作とは同一の畑で同一の作物を何度も繰り返し栽培すること事を指すのですが、じゃがいもは連作を行うと土壌のバランスが崩れ、単純に生育が悪くなるだけでなく、病害や寄生虫が発生しやすくなるのです。ジャガイモに限らず、ナス科の植物は基本的にこの性質を持ち、例えばジャガイモの後に茄子を植えた場合でも連作障害がおきる場合があります。そのためジャガイモを栽培するときはナス科の野菜を3~4年作ってない畑で、堆肥と元肥を入れて耕してから作付けするといいでしょう。
じゃがいもの生態
直立する地下茎は50cm~1m程度の高さにまで成長します。葉の付け根から花茎が伸び銭単位多数の花をつけ、花は星型で黄色い花心と5枚の花弁を持ち、色は品種により異なり、赤、白、紫と様々。受粉能力は低いですが、品種や条件によっては受粉してミニトマトのような小型の果実をつけます。果実は熟するに従い緑、黄色、赤へと変化しますが、落果しやすく完熟するのは稀です。ちなみにこの実にはアルカロイドという毒性があるため食べれません。
じゃがいもは茄子の仲間です。
じゃがいもは実は茄子と同じ種類の野菜でナス科ナス属の多年草です。ちなみにナス科の野菜にはピーマンやトマト、それと食べ物ではないですがタバコもナス科に含まれます。
茄子とじゃがいも全く味も見た目も違うのにと感じると思いますが、それもそのはずです。我々が食べている茄子は茄子という植物の実ですが、じゃがいもは地下にある茎が肥大したもので塊茎といい、日中の光合成された養分が夜になって茎に蓄えられてできたものなのです。
じゃがいもという名前の由来
これには諸説ありますが日本でのじゃがいもの歴史はジャワ島のジャガトラ(ジャカルタの旧名)から伝来したことが始まりでしてた。ジャガトラから芋はジャガタライモと言われ、それが転じたという説やジャワ島のジャガトラから由来したためジャワの方をとってジャワイモが転じたという説などがあります。ただ一般的にはジャガトライモが転じたという説が信憑性があるようです。
じゃがいもにはいろいろな地方名が存在する。
またじゃがいもにはこんな呼び方も存在します。
- 二度芋、三度芋・・2または3回収穫できる事から
- お助け芋・・・飢饉から救ってくれたから
- 善太夫芋・・・1748年に信州より種芋を移入した飛騨の代官幸田善太夫に因む。
- 甲州芋・・埼玉県や愛知県などの地域ではこう呼ぶこともある。清太夫が甲州から伝来させ飢饉から救ったとされているためである。
- イモ、エモ・・アイヌ語で日本語の芋が由来。
じゃがいもの歴史が物語るような呼び名が多いですね。ではこの後はそんな歴史も振りかえってみましょう。
まとめ
じゃがいもは日本に伝来してきてから絶え間なく進化しそれにより味、質、じゃがいもの病気への耐性など日々向上していっています。これには人々の努力があり、そうした努力により私たちは安全でおいしいじゃがいもが食べられています。かつて日本の危機を救ってくれたじゃがいも、我々はこれからも身近な存在としてじゃがいもという野菜を育んでいくのではないでしょうか。
じゃがいも選びのお役に立てたでしょうか?じゃがいもの歴史なども非常に興味深いものになっています。まとめてみたので見ていって下さい。
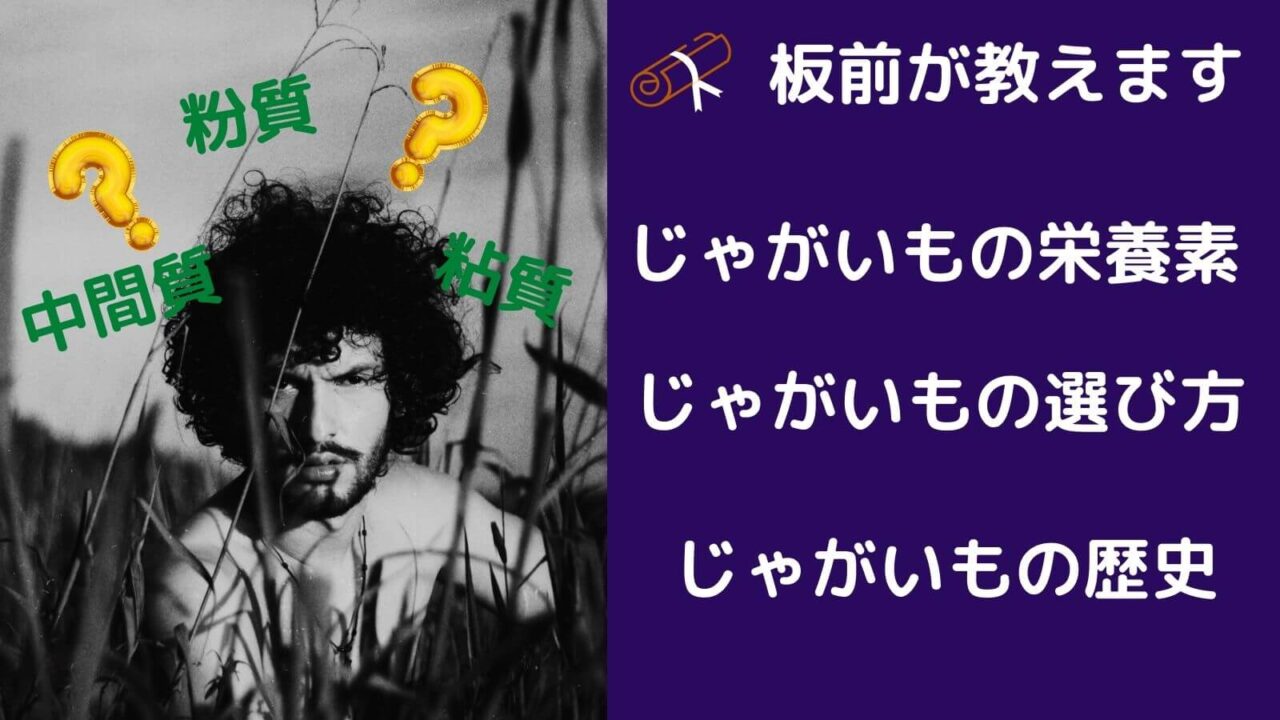

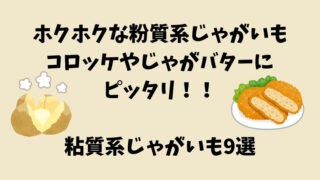
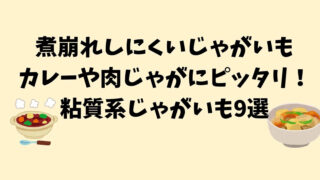
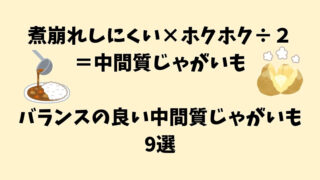

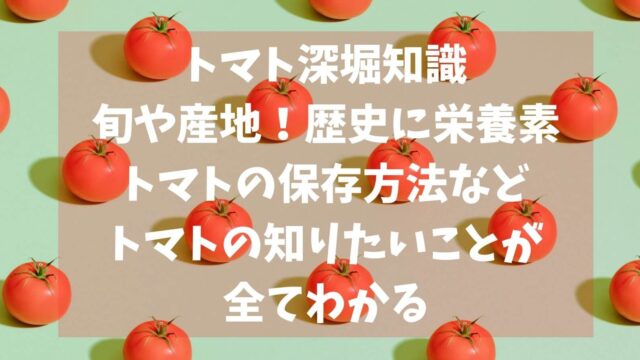


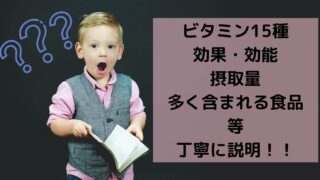

-320x180.png)